| サイト内検索: | |
つくもがみ貸します
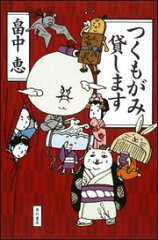 【送料無料】つくもがみ貸します |
■巷説百物語を薄めた感
「つくもがみ貸します」は畠中恵による江戸時代を舞台とした小説作品である。畠中恵といえば「しゃばげ」などに代表される妖怪モノの小説を書く作家...らしいのだが、彼女の作品は本作が初めてなので、他の作品と比べてどうこうということはよくわからない。とりえず確かなのは歴史物を書くのに慣れているようで、文章がこなれており、当時の文化がわからないと理解しがたい筈の作品にであるにもかかわらず、すんなりと文章が頭に入ってくる点が心地よい。
本作品における「妖怪」である「つくもがみ」は漢字では付喪神あるいは憑喪神などと表記し、長く大切に使われた「物」に魂が宿ったものを言う。主人公二人は現代で言う所のレンタルショップの経営者なのだが、彼らの貸しだす商品には多く付喪神が混在していて、貸し出され先で見聞きした事をブツブツ呟く、という設定で物語は進む。
と、このような説明を最初に聞くとファンタジやホラーが嫌いな人はまゆを潜めそうだが、その心配はあまりない。確かに彼らが妖怪として活躍するシーンは多々あるのだが、彼らの物語中での役割はさほど重要なものではないからだ。本作品はミステリ的な構造をもっており、彼らは謎解きのためのツールとしては確かに頻繁に活用される。しかし彼らの活躍は現代劇で言えば盗聴器や単なる聞き込みに値する程度のものであり、彼ら無しで成立しない物語とは思えないからである。
むしろ非常に巧みだなと思ったのは彼らの利用の仕方である。普通小説というのは「主人公の視点」あるいは「神の視点」にて描写されるものである。過去の出来事、主人王の生い立ちなどを語る際にはどうしても説明口調の神の視点が増えるものであり、それは増えれば増えるほどどうしたって読者に「作り物」を意識させることになってしまう。
ところが、本作品のそういった情報は、付喪神たちの「ムダ話」の形で読者に提供される。いろんな時代にいろんな場所においてあった付喪神の視点で過去を語ることにより、「神の視点」という小説内の冷静に考えると不自然な約束事から解放されているのだ。どこかでこの構造はみたぞ、と思ったらなんのことはない「吾輩は猫である」だった。そう考えると先進的だな、あの作品は。
さて、そういう構造的な面白さや文章力の巧みさによってするすると読まされたものの、ミステリとして捉えるとなんだか物足りない。あぁ、そうだったのかと納得する快感もないし、最後のあの展開は正直物語中盤には予測できてしまった。何か一つでいいからあっと驚かせてくれる仕掛けでもあればもっと楽しむことができたと思うのだが、実に惜しい。
|
Copyright barista 2010 - All rights reserved.



